エドモン・ダンテス(モンテクリスト伯)の如くに自らを多摩プラーザに幽閉し、身体が不自由になってからの山口勝弘に強い関心はあった。それ以前の山口勝弘は日本には稀な強固なアバンギャルドであった。しかもエリートでもあった。幽閉後の山口からは健全な肉体が去り、現実に所有していた自由も去った。しかし、精神の自由、あるいは自由な精神は山口から去ろうとはしなかった。何者もそれを侵犯する事は不可能なのだった。勿論それは老芸術家の我執とは余りにもかけ離れたものであった。
山口勝弘は滝口修造氏等の実験工房のメンバーであった。滝口修造の知性の総体が実験工房の枠組みをゆるやかに価値づけていたと思われるが、その、ある種の知性による芸術的倫理観の如き世界観は日本の有象無象の近代運動ではひときわ光彩を放っていた。
昨日、山口勝弘の部厚いスケッチブックをのぞき見て、私は山口の中に流れ続ける滝口修造的世界を初めて実感した。私が山口勝弘の多摩プラーザの小屋で魅入っている彼の絵と、シルクスクリーンと、そして山口のスケッチブックの多様な記録、そして色んな展覧会のカタログ、つまり大山口のキャリアという歴史が、彼の不如意な今の身体故の極小空間にメディアとして溢れ返っている。空間には(建物の)意味はない。そこに充ちるメディアの光芒こそが実体なのであった。
幽閉の身体自由な精神は山口勝弘の宿命でもあった。
怠惰に弛緩した自由は本格的な価値を産み出さぬ事が多い。山口勝弘の表現活動も五体満足の壮年期までは、日本には稀な知的倫理性を備えていたが、やはりアバンギャルドの限界を出る事はなかった。マレーヴィッチの至高主義への共感を度々山口から聞いたが、その至高主義はそのまま、日々の生活、身体からの遊離主義でもある嫌いから逃れられぬ。山口勝弘が身体の自由を失い、多摩プラーザに幽閉されてからの全ての活動に着目するのは、彼の至高のアバンギャルド性が人生の宿命とも考えられる自然な成行きによって開放されつつあると感じたからである。
山口の今のドローイングは壮年の活力と技術に満ち溢れたものではない。稚拙では無い、古拙でもない。しかし、アア、うまいなと思わせるものでは決してない。どんなアバンギャルドの作品でも身体のエネルギーと五体のテクニックに支えられているものは少なくない。その点、今の山口の作品にはそれが無い。しかし、描く、イマジンする山口の精神の自由はたぎり返っている。それだから、山口の今の作品は精神そのものが画筆をあやつっている如きが明らかにある。
人間の生命は身体だけに宿るものではない。近代芸術、あるいはより狭義に前衛精神も然り。それは時に病み、傷ついた身体から産み出される事もある。
山口の多摩プラーザ幽閉生活から産み出されつつある生命の自由への讃歌とも呼びたい連作に着目するのはそれ故である。
老人の智恵と子供の身体が産み出す、新しい世界がそこにはある。
生老病死の宿命から誰一人として自由にはなれぬ。
しかし、山口はその精神の至高力によって、自分の身体をロボット化し、精神の力で、ある身体の未熟状態をパフォーマンスしてみせているのである。
カタログには一九二四年のマルセル・デュシャンの肖像写真が三葉収録されていた。一葉はどうやら口紅を塗り、アイ・シャドーをして女装したデュシャンだった。もう一葉はマルセル・デュシャンが女装を自作自演したローズ・セラヴィという女性名のポートレート。森村泰昌氏の変身、変装芸術はデュシャンに遅れる事七〇年もの時間が経っていたのかと、憮然とする。森村氏の場合はそもそも模倣を模倣する事を表現するという二重の模倣がデュシャンと異なると言えば異なるのだが、それを何度も繰り返して、方法の如くになぞって見せるというのはどんな意味があるのであろうか。芸能と芸術の差異の消失をも表わそうとしているのだろうか。
山口勝弘さんを一年振りに訪ねたら、デュシャンの話しが出た。
「僕はもともとシュール・レアリズムはあんまり好きじゃなかったんだ。だけれども僕のヴィトリーヌの名付親が滝口修造さんで、ヴィトリーヌっていうのはフランス語で飾り窓という意味なんだ。滝口さんが阿部展也の協力を得て作った本、滝口さんの詩と絵画の本なんだけれど、それを読んでいたら、滝口さんの詩の作り方が解るようになったんだ。そしてねェ、滝口さんがフレデリック・キースラーを知っていた事もハッキリと解ったんだ。
キースラーの回顧展がドイツの生まれ故郷で開催されることになってね。だけど僕のキースラー論はまだ外国語に訳されていなくってね・・・残念だよ。キースラー夫人とは随分手紙のやり取りして、インターメディアしてね、あの論は書いたんだけれど・・・。
そう、ヴェネチアのペギーのところのキースラー展見てきたの。ペギーはね自分のギャラリー作ろうとして随分キースラーと話し合ってアイデアも作らせたのね。でもキースラーのアイデアはどんどん進化してしまって、金がかかり過ぎるって、ペギーは随分こぼしてる記録がこんなに残ってるよ。
キースラーは勿論知ってるだろうけれど、かたつむり型の劇場計画を作っててねェ。ああいうのはまさに幻視者としてのキースラーね。だけど情報というのは一種の夢、みたいなものなんだ。
僕の夢はね、色もついてるし、この頃のは音もついてくるからね。オーボエで始まる交響曲みたいなのが鳴りひびいてねェー。ペギーのところの展覧会見たの・・・。あったでしょう。あの、のぞき見るプロジェクト。キースラーは何かを視るって事の意味を、穴みたいなモノからのぞくって事にその究極を見ていたんだ、キット。だからネェ・・・君、キースラーとマルセル・デュシャーンは絶対、彼等は深い仲だったんだ。」
「キースラーとデュシャンは何かコンタクトしてたんですか。」
「イヤ。……アレは深い仲だったに違いないんだ。」
芸術家の深い仲ってのを私は知らない。しかし、何故か少し計りドキッとした。マン・レイのデュシャンの女装の写真を瞬間、思い出したからなのか・・・それで俗なセクシュアルな関係を想像しちゃったりして、誠に私は俗に沈んだ非芸術家である。
そうか、フレデリック・キースラーもマルセル・デュシャンも、共にのぞきに関心があったのか。のぞくっていうのは個人のそれも含めて、今のマスメディア、マス・コミュニケーションの本体だからなァ。今風に言えば視線のテロリズムとでも言うんだろうな、表象の記号の連中は。
彼等は一体何をのぞこうとしていたのかな。より深く見る、より遠くを視る、というのはアーティストの宿命だろうが、彼等はそんな俗論さえも通り越して、デュシャンの言を借りて言えば、眼球の網膜の表面をのぞき、そこに張り巡らされている神経の無限の錯綜、迷宮を直接のぞき見ていたのだろう。つまり精神を構成する神経の森の仕組みそのものをのぞこうとしていたのだ。
アルチュール・ランボーが詩を捨てたのも、マルセル・デュシャンが芸術を停止して、チェスの世界に隠れたのも、その結果なのだろうと思う。
芸術家は、あるいは芸術は何故それを作ろうとするか、よりも、何故、それを停止しなければならないのか、の問題を考えた方が良い答えらしきを得られるのではないかな。超一流の芸術家程そうなのだろう。

山口さんはそう言う。多摩プラーザに引きこもってからの作品には宇宙そのものと言うよりも、大宇宙に浮遊する何かが描かれている事が多い様に思う。本当は打ち上げたいのは山口勝弘自身の身体と精神なのだ。芸術家の自由への希求は強く激しい。それだからこそ、我々は芸術家として敬愛する。
山口さんの今の身体は不自由だ。そうなってからの精神の激しさに僕は驚いている。人間は不自由になって初めて自由の価値を痛切に自覚すると言う俗説がある。俗説の中に、時に輝く真理が転がっている事がある。山口さんの最近の作品を体験して、つくづく、それを感得した。
科学・技術共に永遠に宇宙創成の謎を解き明かす事は無いだろう。勿論、身体と言う無際限の迷路も。 山口さんの作品中に出現する、アダムとイブとか噴水とか、金閣寺、遺跡、そして自画像の数々。僕はそれ等の断片を体験させていただいているのだが、マア、山口さんの勇気に助けられて断言してしまえば、それ等の不可解な集積そのものが、一つの宇宙を表現しているのだ。身体の即物的な自由を失った人間にはある種の尊厳に満ちた特権が与えられるのではないか。
想像をたくましくすれば、山口さんの描く金閣寺のゴールド。その不定形でアブストラクトな形、色を浮かせている宇宙の虚無。
芸術家にとってキャンバスの枠こそが宇宙なのだろう。そこに描かれたゴールドの形、色に問題が秘められているのと同時に、その形、色を成立させている背後の白地や、黒々と塗られた闇、そしてキャンバスのフレームにこそ、問題が浮き彫りにされているように考える。
電脳ギャラリーにも当然、フレームがある。そのフレームの外には現実という、もうこれも宇宙としか呼びようのない、無際限な多様、混沌が広がっている。コンピューターの画面はその無際限さ、混沌を、より明らかに伝えるだけのものかも知れない。
芸術家は何故、こんなに身体が不自由になっても絵を描こうとするのだろうか。山口さんの今を見ると、それはとても表現しない事の不可能性なんて言う宮川淳のレトリックだけでは囲い込めぬ様な気がする。
それでは山口さんの金閣寺のゴールドと、その不定形なフォルムの脇に描かれた白い発光体状のフォルムは、マーレヴィッチの黒と白のバリエーションなのだろうか。遅れて生まれたシュプレマティストであるとの言明はその事の追認であるのだろうか。封印すべきマリアやレーニンを持たぬ日本の芸術家は何をもってチューブ入りの絵の具や洋筆でキャンバスを塗り込めようとしているのだろうか。
山口勝弘は日本近代の前衛芸術運動の始まりであった「実験工房」の若いメンバーであった。その当時の話しも追い追い山口さんに根掘り葉掘りしてみようと思うのだが、それはさて置こう。
偶然や無意識の中に、時に驚くべき骨格の如きが表現されている事がある。この山口勝弘電脳ギャラリーは私のホームページに連載されている。ホームページには同時進行のもう一つのステージが併置されている。宮崎の現代っ子ミュージアムの藤野忠利のコーナーだ。現代っ子ミュージアムは私が設計した建築だ。神武天皇神話のゆかりの地でもある宮崎の美々津の赤土を使って壁の一部に装飾的記号を仕込んだ。その部分が台風で痛み、補修をする事になった。どうせ補修するのならその部分を絵画にしようと考えて、藤野忠利に言ったら、キチンとそれを展覧会にしましょうと言ってくれた。それでそのためのスケッチを描きためている現在だ。どうせならそのスケッチもネットに公開しちゃえと考えて、それが私のホームページのもう一つのステージになりつつある。私の手なぐさみのスケッチで山口さんに挑戦してやろうと言うのでは無い。いくら何でもそれ程の馬鹿野郎ではない。こんな事書くのも失礼極まる話しなのも自覚してはいる。
現代っ子ミュージアムのオーナーの藤野忠利は関西の具体派と呼ばれる芸術家の集まりの、最も若いメンバーである。具体派についてもいずれ考えてみたいが、要するに東京の実験工房が知的で抽象性を好んだのと好対照に身体的具体的なのを好んだ芸術家達であった。要するに考える前に体や手が動いてしまってる人達。藤野忠利はそのメンバーの一人であり、同時に具体派の芸術家達のコレクターでもある。現代っ子ミュージアムはその拠点だ。つまり、気がついてみたら私はホームページ上に実験工房と具体派という極めて対極的な日本の前衛的運動を代表する二つの渦巻きの一部を記録し始めていたのだった。
現実は無限に近い偶然の積み重ねであるが、同時にしばらく時を経てみれば、それを歴史と呼ぶように極めて構築的なものでもある。実験工房と具体派は日本の現代芸術の始まりでもあった。で、あるから多摩プラーザと宮崎市での出来事の記録は実に、歴史的な記録なのである。エヘン。皆さん心して読むように。ネットは立ち読み禁止が言えぬのが良くも悪くもある。
山口さんの金閣寺には何も封印されていない。マーレヴィッチがマリアやレーニンを封印しようとしたようには。では何故、芸術家山口勝弘は描き続けるのか。
封印されているものを解放するためなんだろうと目星はつけている。身体という迷宮に封印されている不自由を解放する。天の岩戸を開いたように。
淡路島山勝工場は淡路一宮町いざなぎの丘に在る。淡路は国産み神話の舞台だ。山口さんが言うように一宮には大社があり、どうやらそれは隠れの宮とも呼ばれているらしい。伊勢神宮に対する隠れの宮なのか、宮崎の高千穂、天の岩戸神話に対する隠れの宮なのかは今は知らぬ。
金閣寺は天の岩戸から洩れ解放されつつある光の状態が描かれているのではないか。山口さんはそれをとりあえず金閣寺と呼んでいるにすぎない。最前線に位置する芸術家はやはり謎をはらんでいる。表現者自身も充分に理解できぬ神秘が秘められている。それ故、人々はその表現に尊厳を認める。山口さんの最新の仕事はイコンにならぬようにしかもイコンの連続である。山口勝弘の頭の中は今ありとあらゆる神秘への関心で溢れ返っている。宇宙の花、遺跡、アダムとイブ、いざなぎの丘、隠れの宮・・・。そして自身の身体。
レーニン、ヒットラーという視えやすいイコンを封印するのに人間は巨大なエネルギーを消費してきた。ワールド・トレードセンターやペンタゴンだってそれがアメリカングローバリズムのイコンであったからこそイスラム原理主義者達によって破壊された。山口さんは新しくイコンを描き出そうとする事によって、しかもできるだけイコンらしからぬ、フォルムを形成しないようなフォルムを描き出すことで、それを成そうとしてるのだ。
金閣寺を描こうとするのは芸術家の意識だ。しかし優れた芸術家の身体はそれを常に裏切る。その裏切り方、裏切られ方こそが芸術の現実なのだろう。
多摩プラーザに隠れた山口勝弘が今描き続けているのはその様な芸術家の現実である。それ故に実に刺激的である。
芸術家のイマジネーション、想像力そのものは幽明界の境界線上を歩き続ける道具だ。芸術家であると自覚している人間はその事を知っている。普通の全ての生活者だって実は皆芸術家である。皆、何かを表現するべく生を成している。しかし生活者はそれを自分の中に見る事を恐れる。自分の中に変な小さな魔物が棲んでいるのを閉じ込めている。その方が通常の生活を容易に成しやすいからだ。小さな魔物の正体は遊び尽くしたいという深奥に潜む本能である。ロゼ・カイヨワからマルクーゼまで遊び=エロスについては数多くの論考がある。論考も又、高度なものは遊びに通ずる。
脱落身心、身心脱落と言う言葉が禅にはある。昨年亡くなった佐藤健から教えられた。禅というのはまだ解らぬ。怪しいなと思う事も多いが、表現というものを考えるに、この言葉は一つのヒントを与えてくれるように思う。妄想の類いも含めたイマジネーション、想像力は現実の身体。そしてそれと不即不離の気持ちから離れたところに出現する事を示そうとしている。
多摩プラーザ、山口勝弘の言う幽閉の宮での表現はそれ故その問題を考えるのに、良い入り口になるだろうと考えた。不自由の枠の中に決然とした自由がある。

山口さんは時代と共に生きている技術に敏感であった。電子技術による映像に精通され、ヴィデオアートの草分けでもあった。
かつて何かの博覧会の仕事で御一緒した際に、有言不実行の人間が余りに多い中で、一人何も言わずに自分のやる事を、ズンズンと進めていた姿が記憶にある。要するに現実に対しても強いのだ。
その現実に対する強さが今は夢の中に現れているのではないか。隠れの宮多摩プラーザに自らを幽閉し、無駄なエネルギーの放射を禁じ、ひたすら想像力の純化を企てる今、山口勝弘さんの実際家としての精神の力は、未見の風景をわしづかみ、五感ならぬ第七感で感じ、それを復元する事が可能になった。
まじまじと山口さんの印度の遺跡に見入っていたら、突然そこにもう一人の人物の作品らしきがあぶり出されてきた。南の印度ならぬ、北の気仙沼の大自由人高橋純男の日ノ出凧の群である。


この人物は本当に凄い人だった。
山口さんは環境芸術という概念を作った人だが、この無名の気仙沼人はその環境芸術を極く極く自然にはやくから実践していた。人物は連凧の名手であった。数百メーターにも高く昇り連なる連凧を時々気仙沼の空に上げていた。何の為でもなく、ただただ気仙沼の空のために。
北の淡いが澄み通った空に浮かぶ凧は凄くアブストラクトだった。そして空に浮かび、小刻みに動くと俄然生気を放つのだった。
山口さんの作品と気仙沼人高橋純男さんの凧とを並べて論じたって、勿論山口さんは嫌がらぬであろう。そんな不自由な枠からは解放されている。かたや、芸術家である事を自覚し続けている意識家。こなた、凧上げであらざるを得なかった市井の隠者である。何変る事があろう。

山口さんの想像力は不自由な身体になってますます飛翔の距離を延ばした。多摩プラーザの部屋から一歩も動かずにデカン高原に迄飛び、あの大高原の風や砂、土の臭い、落日に照らされる小砂丘の影までも触れる事ができたのだ。しかも山口さんは魂の手で直接デカン高原に触れた。この色彩はどうしてもそうだとしか思えぬ。
更に想像をたくましくするならば、ここはエローラの窟院ではないだろうか。中央の巨大な窟院カイラーサではなく、幾つか緩い岩山の起伏を歩いて辿り着く、秘めやかな小窟院。未完の修行僧が掘り続けたといわれる僧院の跡。西向きの岩山にうがたれた洞穴の入り口には大きな牛の象が彫られ、デカン高原を遠望している。石の牛は千年も一歩も動かないで居る。その牛の肩に壮大な落日の朱が差し込み窟院にほのかな光を差し込ませる。山口さんはその光を描いたのだろうと考える。

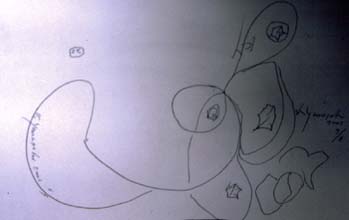
スケッチブックは芸術家の作品の遺跡である。スケッチをして、つまりエスキスをしてから作品にとりかかるのが常識であろうが、デュシャンのような大意識家の表現を考えてみると、その逆もあり得るのか、と思う事さえある。つまり、作品を作り上げてしまって、それから、それを成立させたスケッチに遡行すると言うような事だ。
山口勝弘先生のスケッチブックを一瞬のぞいただけであったが、そこに作品を成立させる過程が示されていると言うよりも、作品との応答、コミュニケーション状態の如き状態が示されていた。二〇世紀芸術の優れたモノが極めて知覚的な状態を目指そうとした事が了解できるような気持ちになった。
先生の最近の作品が多く、シリーズ(連作)の形式をとっているのも、その証明であろう。一つの視覚的作品として集約させ得ぬモノを思考し続けているからだ。思考は常に頭脳の運動状態の内に生まれる。動きそのものである。それは連作の方が示し易いのだ。

山口勝弘のその一点がこれだ。
「若い時に描いたものなんだけれど、コレだけは絶対に売らない。」
と、断言している。
俗人中の俗人である私はその言葉だけに気を取られて、肝心の、その絵の事を尋ねるのを忘れてしまった。
山口勝弘の内には遅れてきたシュプレマティストであるという強い自覚と同時に、シュプレマティズム、及びその芸術家達が成し得なかった事、至高を求めながら、平気で俗な地獄に足を踏み入れる事を試みようとする意志の持続があったのではないだろうか。メディア・アート、環境芸術という俗社会に呑み込まれかねぬ世界に飛び込んでいった勇気は、それ故であったろう。
この絵に現れている、二極指向の趣の発露は、今の山口勝弘が到達した境地を、すでに暗示している。

宇宙と題する絵画を描くのは山口さんの右手である。右手は恐ろしく微妙な手の内の筋肉や、骨組み、血管の内の血圧、そして脳細胞と結びついた無数の神経等の集合体である。それ故、右手に握られた絵筆がキャンパス上に描き出すモノは右手の宇宙が描き出している何者かで、それは言いつめれば右手の宇宙そのものである。
山口さんが右手に力が戻ってきた、と力説したのは、だから山口さんの身体的宇宙が、外の大宇宙との結びつきが強くなったと言う事と同義なのである。
それに考えてもみたまえ。山口勝弘の右手がいかに多くの人々、芸術家達の右手と握手をしてきた右手である事を。それは右手の諸器官が細妙に貯蔵してきた歴史の格納庫でもある。宇宙シリーズに表れた色やフォルムや動きのエネルギーは、そのような記憶の集積回路でもある。とそう考える。「僕は遅れて生まれてきたシュプレマティストなんだ」と自覚している芸術家が表現しようとしているモノは、それに対する者にもある種の自覚を要求する。眼球の神経が連関している知覚をも動員せよ、という強いオペレーションである。

シリーズ、つまり連続したテーマで描かれたものは、その連続の仕方と不連続のあり方を、時間を意識して見てゆく必要がある。同時に、幽閉されたと自分で言っている山口さんの部屋そのもの、その空間が卓越した自意識を持つ芸術家にとっては、それも又、宇宙なのだと言う事も忘れないようにしなくては。
宇宙のとなりに帽子がフッと掛けられている。山口さんの頭脳をくるむ、これも又、宇宙なのだ。帽子の隣りに宇宙があるのは、山口さんが描き続ける色と形も、直接に山口さんの思考そのものを示している事の暗示ではないか。
それを偶然と見るか、必然と見るかで、見る人の世界も解ろうというものだ。
「自分の病気が治りつつある状態を描いているのが宇宙シリーズなんだ。」と山口さんは漏らした。自分でも無意識の中で描いている抽象的な絵画の意味を、山口さんは知りたかったのだろう。「この線は僕の体の血管だったんだよ」「バックの宇宙の色が段々明るくなってきているのは、体が回復している証しなんだ。」
最良の芸術家は絶対的に自分を信じている。誰が何を言おうと。山口さんは宇宙シリーズの絵画群に自分の身体内宇宙を、希望にダブらせて幻視しようとしている。この、生命への渇望は凄いと思う。「禅宗の言葉、不生不滅が今はよく解る」とも述べた。生まれなければ死ぬことも出来ぬと言う絶対矛盾を内包した寸言である。同時に「僕は遅れて生まれてきたシュプレマティスト」なんだとも言明された。沢山のインスピレーションを話されたが、今は整理しない。