
まず行き交う人々の歩調、つまりリズムである。芭蕉が行き交う人もまた旅人なりと呼んだときからすれ違いは出会いになった。デタラメほど難しいものはないと教えたのはクセナキス、ジョン・ケージ、高橋悠治の系列である。あいにく私はそれを数式で表せるまでの知恵を持ちあわせていないが、歩道を行く人は明らかにいくつかの歩調に区分けされる。歩道を五線譜に見立てれば、群行は行列となり、行進となる。歩みの遅い人を早い人が追い抜いていく、その追い抜き方も一様のリズムがある。
次に視線である。男性の平均の視点の高さは一六〇〇ミリ程度、女性のそれは一五〇〇ミリ程度であろうか。これもまたみな一様に正面から前方やや斜め下を向いている。すれ違う人を振り返ることはまれである。つまり一定のリズムを協奏しながらも互いの関心は薄いようである。イヤホンをしている人や携帯をいじっている人が多い。できることならここでこうして歩いていたくなどないのだろう。歩かざるを得ないから歩いている。
これらを鑑みて、そこから外れた人物を探すことにした。リズムを乱す者、あるいはリズムから外れる者である。じっと見ていると誰もが右足と左足を交互に踏み出している。当たり前である。交互に踏み出さねば前に進めない。右足と左足を入れ替えながら歩いている人はいないだろうか。こういう意識過剰な人はそうはいない時代である。では歩いていない人はいるだろうか。歩道にいつまでも留まる人。これはいくらかいる。信号を待つ人。待ち合わせをする人。つまり何かを待つ人である。歩道を俯瞰してみてそういう人を探すうちにふと視線の下に何かが引っかかった。そのまま視線を下にやると老女が座り込んでいた。これが私と老女の最初の出会いであった。
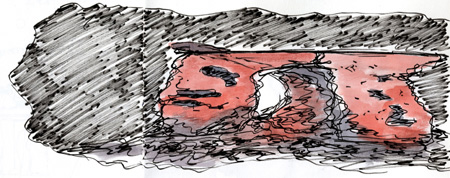
それで即興でシナリオを付けてみた。
『朝の日差しの射し込む時も、宵の闇が覆いかけようとしているときも私はちいさくうずくまって、何をしようとするものでもない。ただその場所に留まり、わずかに動いてはまた静かに座り込む。私はひとりである。容姿も優れたものとは言えない。世間一般には老婆の範疇に入るのであろう。毎日何するという事はない。ただちいさくうずくまって人々の往来を眺めるだけの日々である。そういう私を見て、俗な感性ではひとりは孤独とイコールではないかと思うだろう。しかし、決して悲しげな表情ではないのは容易に見て取れよう。みなが思うほど人々の往来とは退屈なものではないのだ。さらに言えば、私は世の中の構造の一部として生き続ける事ほどはかないものはないとも思っている。そういう私に取って日の光にとらわれずに生きる事は小さな反抗でもあるのだ。
身の回りのものと言えば、三つの黒いビニール袋だけである。世俗に身をさらす上での最低限のものは全てその袋に包み隠している。』
老女は「そんなこと全然思っていない、ほっといてくれ。」というだろう。
実際老女はそこまでの聖というわけではないのは知っている。老女が座り込んでいる通りの一角にいつもやきいもを売りにくるトラックがある。私の知人はその匂いに誘われて思わず一つ買ってしまった。それから少し歩いていくと、どうも下からの視線を感じるのである。なんとその知人は老女を見かねて「やきいも食べます?」と聞いてしまったのだ。そして案の定、老女は「うん。食べる。」と返事をしたというのである。それで私は知ってしまった。彼女は西行とは違うのだ。
それでも私が老女の姿にシナリオをつけるだけで私の中に劇的な空間が生まれるのである。老女がいつもそばにおいているあの袋には一体何が入っているのだろう。そして歩道の脇にちいさくうずくまるその老女の目は何を見ているのだろうか。シナリオの様に人々の往来を見てはいるのだろうが、もっと遠いところを見ているのではとさらに勘ぐってみる。その視線の先はきっと老女のこれまでに関係しているに違いない。
『私は若い時は小町と呼ばれた大層な美人だった。皺を伸ばしてよく見てご覧。』
これでは三島もびっくりの卒塔婆小町である。
『私は若い時からそれは見映の悪い女と言われ、、、』
これもいまいち。現在の老女の達観したような劇的なものが散逸してしまう。目で見えるものを一切信じないというような信念が老女にはふさわしい。
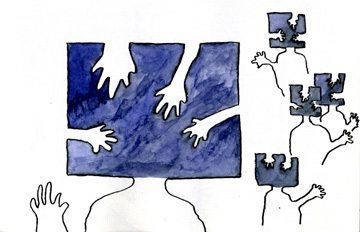
しかし、私が老女を見て感じ取ったその所作は能舞台そのものでもある。ジイッとちいさくうずくまる老女の所作を様式化された表現の一部として見たいという作者の願望がある。さらに作者にとっての老女は世の中を達観している。決して「お風呂に入りたいなあ。」などとつぶやいてはいけないのである。喜劇ならずとも、こうしたプロセスを含めて描けば喜劇的な要素を取り入れることはできるかも知れぬ。
『通り過ぎていく人は私が誰であるかには一切関心がない。私が握りしめている袋と同じ様に私を見ているのであろう。いや、見ているという認識すらないであろう。そこにスキが生じるのだ。つまり、あなたの中の空間に私は忍び込んでいけるのだ。そうやって私は往来の人々を楽しむ術を知っている。ほら、あの男。昨日は飲み過ぎたのか、頭が痛いのであろう。視野が狭くなっている。けれどもそういう男の方が楽しみは大きい。余程楽しかったのか。昨日の事を反芻している。目に見えるものには関心が無い。私は他人が想像する空間を体験しているのだから。』
老女版小野小町は仏法に強くはない。うずくまっている場所を僧侶に咎められても言いくるめることはできないだろう。しかし、現代の僧侶以上に他人の中に入っていくのは得手である。老女の白髪はその修練のたまものであろうか。
『今度は、あの女。日本人ではないな。どれどれ。亜熱帯系の貧しい農村地帯で育ったのか、高床式の木造小屋があるな。近くには川も流れている。東から時折吹く風が気持ち良さそうだ。東京では望めない風景、、、もう過ぎ去ってしまったか。』
老女にとってすれ違いは出会いである。そうして老女は一日、一日人々の夢想の往来を巡っている。少し疲れると腰を上げて、もといた場所から五十メートルほど離れた場所へと移るのである。


例えば、ひとりの美しい女がいる。その女はこれまで何人かの気持ちを寄せて来る男と床を共にし、男は女の枕を借りて寝てしまう。夢の中でその男はついに女と添い遂げるが、晩年には年老いて足腰の立たなくなった女の糞の世話をする介護の日々を送りながら死んでいく。男は目覚めると浮き世の美しさのはかなさを知り、みな女に興味を示さなくなってしまう。いつも女はそれを嘆くのである。
私が出会った老女は、いわばそういう夢の中の年老いた女の姿である。夢の中の老婆もまた、自分の夢想に楽しむときもある。その多くは逆に自分が美しかったころを振り返るものだ。夢の中の年老いた女はさらに夢の中で昔に戻ろうとする。しだいに老女は自分が夢の中の人物なのか、夢の中の夢の人物なのか、夢の中の夢のさらに夢の中の人物なのかもわからなくなってくる。すると結局、老女は永遠に老女であることから逃れることができないではないか。かくして老女は通りにうずくまって人々の往来を眺めるようになったというのである。
『何度日の光が現れようとも私は老女のままだ。夢を見ていたはずなのにどうして覚めないのだろうか。』
老女はつぶやく。
『あの顔もこの顔もみんな覚えのある面(ツラ)だ。ただ、いつ見たのかだけがわからない。そのとき若かったのか、年老いていたのかさえも。』
老女が腰を上げるとき、すなわち他人の夢想を歩き渡るのをやめる時は決まって老女自身がそのようなことに想いを馳せているときであった。

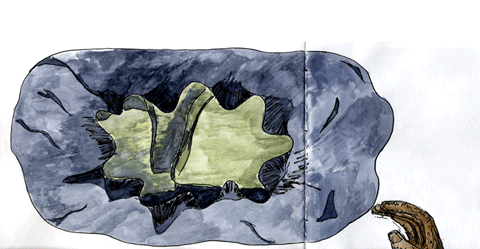
さて、永遠に老女であるとはどういうことか。文化・宗教によって時間に対する考え方は様々である。ニーチェの永劫回帰によれば今起きている事は全て体験済みの事だという。キースラーがエンドレスハウスにヴィジョンを見たときも時間は巡る構造を持っていた。終わりも始まりもない時間である。そういえば宮脇愛子の『うつろひ』の展覧会のタイトルも「終わりのない、始まりのない」であった。
老女の場合はちょっと違うようだ。私が見てきた老女は往来の顔をどこかで記憶しているようだった。それについては確かに永劫回帰と共感できる。ただ、老女は自分がこの世に誕生した以前のことにはあまり注意を払ってない。老女が食べていたのは、そんな哲学的やきいもではなかったはずだ。当然媼も私も西行やニーチェではない。そのような人間にはニーチェ以降も依然として時間は始まりも終わりもある。自分が生まれる前の世界を確認することはできないし、それは自分の死後も同じである。しかし、しかしである。老女の場合に限って、彼女はやや生き過ぎた。その結果老女は今、ここにいる自分を確信することもできなくなった。そうして老女の時間は「終わり」を消失したのである。もちろん全ての人にとって時間を外部の視点から俯瞰することはできない。誰かが死ぬと「その人の時間が終わったのだな」と他人が外から解釈するだけのことである。死んだ人の視点でそれを意識できるとすれば死の直後の残留思念だけだと憶測する。あるいは、ダンテの『神曲』のように死後の世界を信じる人にとっての時間は終わらないのかも知れない。そうした多様な価値観を受け入れた上で、老女の時間は始まりのある終わりのない時間となったと考えてみたい。すると老女はこう考えるに違いない。
『確かに年老いた姿をさらすのは美しかった私には忍びないことである。できれば、誰も私と気付かないで欲しい。しかし、唯一私が本当に恐れるのは永遠に死はやってこないのではないかという恐怖である。それだけを恐れて、今私はゆっくりと自殺しているのだ。』
今日の朝も老女はうずくまっている。クビからポンチョのようにかぶった灰色のシャツは昨日の雨でまだ湿っている。朝食はどこからかもらってきたスープのない素うどんである。
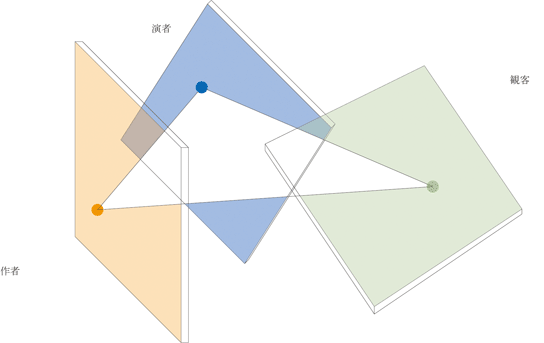
ともあれ媼は終わりのない時間に向かって自殺している。そう考えてみることで死を自覚出来ない私と媼の距離は非常に遠くなる。
老女はジっとうずくまって死を待つのみであるから、必然的に老女の衣服は死装束である。老女に必要な小道具は他にあるだろうか。
『老女の背中はマユのように丸い。老女がツツッと通りを滑るときは杖があった方がよいだろう。老女が持つのは「山姥」や「恋重荷」で使われる鹿背杖が良い。早速、意気込んでスケッチする。が、どうみても駄作である。故に公開はしない。いざやってみると杖一つでも意外とディテールを必要とされる。例えば媼は杖を右と左どちらの手でつくのだろうか。媼の身の丈はどれほどか。素材は何が良いかなどなど。媼はいつもビニール袋を三つ持ち歩いている。それを片手で運ぶことは難しいに違いない。杖を持つ手でも袋を一つは持てる必要がある。云々。』
試行錯誤している私のスケッチを待たずして、老女はカメラの三脚の一本を拾ってきた。老女はそれで充分だという。やはり作者のおせっかいが過ぎたようだ。確かにそれであれば折りたたみもできる。袋と共に動く時は袋にしまってしまえば良い。かくして老女は三脚を杖にして通りを歩く様になった。
『どうも演者のところへ上手く飛べていないなあ。もう少し別の仕掛けを考えねばならない。』
作者はつぶやいた。

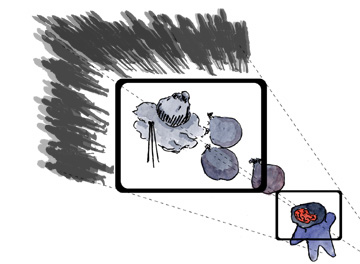
『例えばハリウッド映画はまさに資本主義帝国における楽観的娯楽の典型である。歴史的価値のあるものは少ない。しかし、単純に観て面白いものが多い。まさに娯楽そのもの。さらに映画は元来時間をともなったヴァーチャルな体験である。いわばディズニーランドのアトラクションに近い。レールを滑る山車に載って順々に物語空間を巡るわけだ。ヴェンチューリのラスベガスもその類のものではあるが、ヴェンチューリはあくまで建築物等のスタイル(見えるもの)に主眼を置いており空間の物語性(見えないもの)についての記述は少ない。「less is bore」や「アヒル」も見えるものの問題に集約される。では、「ハリウッドもの」空間が持つ物語性とは何か。大きく二つに分けて考えることができる。すなわち観客の過去の体験や記憶から生まれるものと作者の想像力から生まれるものである。
映画『トゥルーマンショー』は巨大な映画セットの中で育てられた子供の成長を十年以上かけて見守る空想のテレビ番組である。ジム・キャリー演じる主人公の親や友達は全て役柄であり、実はそれぞれ俳優が務めているというわけだ。このテレビ番組「トゥルーマンショー」は映画『トゥルーマンショー』の劇中劇である。「あなたたち観客も同じ状況におかれている可能性があるのですぞ。」という作者のシナリオが観客の日常にまで侵入してくる。すなわち自分の親は親の役を、親友は親友の役を演じているだけの疑似世界ではないのか。そういえば、親しい人が急に全くの他人に思える時がある。そうではないと誰が保証できるのか、といった具合だ。随分前の映画であるが、アナログ型SFの趣があって確かに面白い。つまりここでいうヴァーチャルは見る人の現実の体験や記憶を刺激することで生まれるものである。映画『マトリックス』で巨額のマネーをつぎ込んで作られたハイテク型SFを意味論としてはとっくに先取りしている。さらに注目したいのはその様子を十年以上も娯楽番組として楽しんできた圧倒的観客の存在が描かれていることだ。視聴者として描かれた彼等は番組で起こっていることが自分にもあてはまるのではないかなどとは一切考えない。番組によって想像力(その本性は俗な好奇心に過ぎないのだが)を刺激されるとしても、それは極めて受動的である。視聴者は何かを深く考えること無く楽にヴァーチャルを体験するが、その分番組プロジューサーの制御の枠から出ることもない。あくまで劇中劇「トゥルーマンショー」は作者の想像力から生まれたものである。では、その劇中劇を視聴している人を視聴している我々はどちらの側の観客であるか。いずれにしても、ここで描かれた圧倒的観客(視聴者)こそが資本主義下における大衆像であることに疑いの余地はないだろう。
作者の想像力による観客傍観型には多くの事例があるが、少しだけそれについても述べておく。典型的なものは『スターウォーズ』。ジェダイと帝国の宇宙を股にかけた攻防を誰も自分の体験に置き換えて考えはしないだろう。むしろ旧三部作の後に作られた新三部作に見られるように、クローン戦争など現実の技術発達に伴って後から得られた未来像を物語に取り込むなど、作者の方が現実を模倣して空想世界を創っている。観客は七十年代こそは作者の描く未知の宇宙空間そしてスペクタクルに胸をときめかせたが、新三部作は旧三部作を楽しめた時代に対するノスタルジーに浸っているに過ぎない。作者の想像力は旧三部作で留まっている。我々はもう火星にも金星にも宇宙人はいないことを知ってしまったのだから(もちろん遠いはるかかなたの銀河系に宇宙人がいることは依然として否定できないが)。
インターネットのステージと頭の中の夢想のステージにもそういう違いがある。ネットの観客は現在のところ極めて受動的である。言うまでもなくネットの本質は誰もが等価であり、即座に反応を示すところにある。しかしその手法がせいぜいブログに留まる限りネットの本質を上手に捉えているとは言えない。頭の中の夢想は逆に誰もが自由に作者として想像力を発揮できる。しかし今度はそれを共有する技術がない。つまり観客のいない劇場である。もしネットにおけるステージを利用して頭の中の夢想のように誰もが作者の視点と観客の視点を自由に行き来できれば「ハリウッドもの」のように二項対立に納まらない空間を獲得できるのはないだろうか。』
老婆心ながら観客から作者に伝えてみたいと思う。

卑弥呼の古代政権を想像してみる。おそらくこの頃の社会システムはより宗教的側面を持って然るべきであった。神秘的なものへの傾倒は指導者を支持したに違いない。卑弥呼政権が九州にあったのかは定かではないが、古代の儀式空間が今も九州に残っている。宗像大社である。宗像大社は沖津宮、中津宮、辺津宮の三宮の総称である。それぞれの宮には俗に宗像三女神と言われる田心姫神(たごりひめかみ)湍津姫神(たぎつひめかみ)市杵島姫神(いちきしまひめかみ)が祭られている。この三女神は古事記に登場する。すなわち、須佐之男命が伊耶那岐命によって追放された後、天照大御神の治める高天原へ向かった時のことである。須佐之男命は邪心のないことを伝えるために天照大御神とうけいをした。天照大御神は須佐之男命の十拳の剣を受け取ると、それを三つに折り高天原の聖なる井戸でふりそそぎ、噛みに噛んで吐き出した息の中に三女神が生まれたというのである。その一つの辺津宮に宗像大神降臨の地と伝えられる「高宮祭場」が残っている。悠遠のいにしえよりこの地でお祭りが行われて以来、現在も神籠(ひもろぎ)・磐境(いわさか)という祭事が古式にのっとって続けられている。この古代儀式空間を訪れてみると、そこには何も無い。丘の上の森に囲まれたわずかなスペースがあるのみである。木と木の間を白い布で結んでそこを囲んでいる。なんとなく神聖な空間であることはうかがえるが、ただ人々はそこに降神があったと信じている。コンセプトだけの空間には実物は必要ないということであろうか。
現在の日本でも大嘗祭などの儀式が天皇即位の際に行われていることは良く知られている。今はまだ儀式と建築の問題に多くを言及しないが卑弥呼の時代の社会や宗像大社の高宮は現在よりも強く国家や空間が儀式とともに成立していた時代のことである。
対して技術革命は常にその傾向と逆行する。農耕革命は貧富の差を生み、ムラ長システムを生んだ。穀物を蓄えることに成功した者はムラの指導者となった。ブルジョワジーの誕生である。支配社階級はムラの安全を守る代わりに穀物を要求した。さらに二千年近く経って産業革命が起こり、ようやく立て前としての政教分離が近代国家の基本となるまでに至った。こうした宗教的側面という「見えないもの」の力が風化していく過程でオウムの如きスタイルの宗教は発生した。すなわち精神的な帰依を伴わない宗教の成立である。
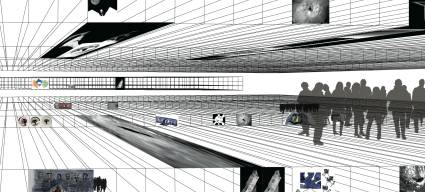
一方、サティアンは宗教施設でありながら電子機器の倉庫でもあった。
「電子は精神に代われるか。」
『マトリックス』の如き仮想空間をオウムは現実を壊す(すなわち、その存在を不安定にさせる)ことで安定させようとした。ダンテやテラーニと違って、その為には精神は未成熟なままでも差し支えがなかった。故に彼等の現実世界の聖堂であったはずのサティアン自身は現存しない。
オウムが壊そうとした現実は、実は既に不安定構造物である。それは次々と忘れることを繰り返すことで不安定な状態を安定的に更新させていくものだ。電子はその速度を大幅に上げたに過ぎない。特に忘れていくスピードには目を見張るものがある。不安定構造物においては全てに速度を与えなければそのかたちを維持できないのだから、必然的に動かないものには価値が発生する。携帯電話とインターネットが世界的に普及し始めた現代こそ「不動人」(immobile man)の意味を自覚せよと山口勝弘はやや自嘲気味(本人の言)に言う。山口の手描きの絵画にはこのことをテーマにした自画像が多数ある。山口によればこの「不動人」(immobile man)とはそうした現代の特性を良く捉えたイタリアのあるアーティストの展覧会タイトルである。
動かない=(イコール)何か。例えば山口の言うように壊れた身体か。今流行の誰もが言うような身体性と山口のいう身体はおそらく異種のものだ。一般に前者は暗黒舞踏やアングラ演劇の範疇に納まる。土方の身体性は物理的な動きの中に精神世界をみようとしたものだし、アングラ演劇のそれは芸術で言えば具体派に属するものだろう。それに対して私が興味を示していた能は様式美である。エレガンシーを伴うものだ。文学の世界ではこれは既になされている。世阿弥はそれを幽玄と呼んだわけだが、私はそれをウェブに見ようとしたのだ。

ダンテウムとウェブの差異は主体の数に他ならない。ダンテウムを旅するのはあくまでも『神曲』を書いているダンテである。もしくは作者としてのダンテを演技したテラーニである。主体がはっきりしているが故に安定した仮想空間を保つことはできるが、それはダンテ(あるいはテラーニ)以外の人間のことなどは考えられていない。ウェブの主体は複数でありながら本人にとっては一人であるという特異な点を持つ。本人にとってはダンテウムと同じ様に自分のためだけの空間だが、俯瞰してみれば次々と主体は入れ替わっていく。いわば不安定な安定である。
こうした空間は日本の建築史では茶室に現れていた。堀口捨巳の『茶室研究』には利休の待庵を例にそのことが示されている。堀口によれば、利休は一つの空間のホストとして一日に一人だけのゲストを迎えていた。その日の空間はその人のためだけに用意されたものである。これだけであれば日替わりダンテウムのようなものだが、利休はさらにしつらえという小道具を凝らした。茶碗や茶釜などの茶道具はもちろん掛け軸や花までをその日展開される客人との会話(これはかなりシビアなものだったはずだ。)のコンセプトを明晰に示した。特に秀吉との茶席では二人はそれを見るだけで会話をする必要がなかったに違いない。さらにしつらえに対する意識はゲストを迎える露地へと展開する。露地とはゲストの足取りのデザインのことである。このときゲストの側からも視線のデザインを利休に提出する。視線は当然ゲストによって違うものであるし、ホストはこれをコントロールすることはできない。こうしてホストとゲストのやり取りの上に露地空間が展開されるのだ。躙り口の脇に一つだけ外れて置かれた飛び石はその象徴である。

明治通りと諏訪通りの交差点を渡ろうと信号待ちをしているときに飛び込んできた女子中学生の会話である。オジさん世代は耳を疑うだろう。私も疑った。オンライン上で付き合うとはどういうことか。しかし、この中学生は利休が生涯をかけて見出した空間をあっさりやってのけている。すなわち一度目の「オンラインで」でホストがゲストを迎える日取りと茶室を決め、二度目の「オンライン上で」でしつらえを配してゲストと会話を交わし、最後の「現実でも付き合うことにしたの。」でこれまでのホストとゲストの観念的なやり取りの上に現実の露地空間を成立させている。ウェブは現実空間とたくらんで、こうした不安定な安定を可能にさせるフィールドとなる。
上の絵は深夜の大黒ふ頭に足を運んだ時のものである。ここのPA はいわゆる不良があつまるところで有名なわけだが、いまどき暴走族などの類はいない。このときは紫色をした数台のワンボックスカーに馬鹿でかいスピーカーが載せられていた。どこかのクラブイベントの帰りなのだろうか。載せられたスピーカーからは爆音ともいうべき音量でクラブミュージックが溢れ出てくる。若者はその音にのせて、なにやらあやしげなダンスを踊り始めるのである。直径五百メートルほどの何重もの立体交差のスパイラルで囲まれた大黒ふ頭はアッという間に劇場へと変身してしまった。ふと、宗像大社の高宮を思い出した。高宮は降神を信じるアニミズムによって空間が儀式とともに成り立っていたが、ここは爆音と若者のダンスが劇場空間を安定させている。一旦音楽が止まってダンスをやめてしまえば、もとのPAに戻ってしまう極めて不安定な空間だ。
もちろん現在のブログなるものは不安定構造物を体現できてない。それはウェブと現実が互いに寄りかかっていないからだ。繰り返しになるがダンテウムを成立させたダンテとキリスト教のフィールドは「見えないもの=安定」の構図に支えられていたのに対して、この時代の現実とウェブは「見えないもの=不安定」を繰り返すことで安定を保つのである。吉坂隆正が不連続統一体を唱えてから二〇年余り。不連続の連続は当たり前の時代になった。それが現代人の忘れ易さに現れているのだ。それを前提としないデザインなど成立しない時代である。六本木ヒルズやミッドタウンなどの商業建築が次第に一世を風靡し始めているのも消費の本質が現代人の忘れ易さと重なるところが大きいからである。しかし商業建築にその答えを求めていくのではあまりに考えが早急ではないか。
近代能楽劇場と二見浦秤動劇場はそうした欲求不満に対するエスキスであった。まがりなりにも上手くいったとは言いがたいが、不連続の連続という状態は意図しないところで体現していた。目に見えるものを、かたちをデザインするだけでは不充分である。
再び見えないものに返るときが来た。しかし、それがまたも精神的なものなのかは依然として要を得ない。次の段階に進むべく、一度劇場の幕を下ろそうと思う。
001 青いハンカチに関するルポルタージュ
002 黄色いハンカチに関するルポルタージュ
005 山口百恵と松田聖子に関するルポルタージュ
007 宝塚歌劇団に関するルポルタージュ
009 妹尾河童に関するルポルタージュ
011 大隈重信像に関するルポルタージュ
013 社会構造に隠された演劇性に関するルポルタージュ
017 結婚式会場に関するルポルタージュ
020 オスカー像に関するルポルタージュ
023 二冊のスケッチブックに関するルポルタージュ
030 選挙