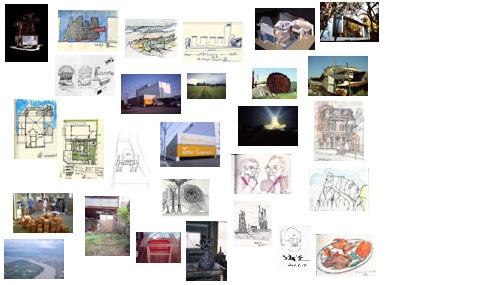|
|
カバーコラム7 石山修武 |
|
|
|
 
064 佐藤和則唐桑町長2
町長になった佐藤と私の縁は遠ざかった。唐桑には私は用のない人間になった。私の代わりに、民俗学、地域学の結城登美雄が佐藤の粘り強い相談相手になった。しかし、華々しい成果は得られなかった。地方の小さな町が対面している困難さは、一人や二人の創意工夫や努力だけではどうにもならない。佐藤はそれでも頑張って多くの改革を成したが、風の噂は流石の佐藤も次第にシニカルになってきたとも伝えた。
私は田舎の町を流れ歩くのから、足を洗い、ただの設計屋になった。途方もないエネルギーの浪費をする事も無くなった。しかし、今度は私の方がもんもんとした日々を暮らす事になった。蕩尽の日々を懐かしむ事にもなった。大漁旗と竹のやぐらと廃工場を使った臨海劇場は今は跡形もない。きれいサッパリ何も無い。しかし、あの記憶は当事者達の胸の中に痛切に残り続けている。
「竜宮城みたいだった」と懐かしむ者も居る位だ。
時は流れる。時代は廻る。
何年振りだったか、佐藤和則町長と再会した。唐桑町は来年3月気仙沼市と市町村合併の行政改革システムに従って合併と合なった。佐藤も考えに考え抜いて、町民と共にそう決断した。恐らくは苦渋の決断でもあったろう。合併後の佐藤の身の振り方は今のところ誰も知らない。佐藤も何も語らない。私も尋ねない。
日本の田舎の未来はどうなるのか。
鶴見俊輔みたいな智者は「品格のある地域」を静かに唱えたりする。要するに経済の活性化とかはさて置いて、静かに品格を持ち枯れてゆくしかないの考えだ。体制=システムの改革なくして、地域の改革は無いというのは正論である。しかし、正論の大半は俗論に過ぎぬのも真理である。鶴見俊輔等の言う地域の品格とは、人口減少、経済力の縮小を前提とした実に自然な論理の帰路にしか過ぎない。
要するに一九五〇年代池田勇人の内閣が所得倍増、経済成長を唱え、日本全体の活性化をうながしたのと裏腹な論理だ。透徹した史観は近未来日本に経済発展はあり得ない、人口だって減少する一方だと知らしめる。その現実が一番端的に波及するのが地方すなわち田舎だ。資本は都市に集約しやすく、田園や山野には集積し得ぬからだ。それで、地方=田舎はキレイに枯れてゆくしか未来は無いと言う、必要以上に文化的な認識が生まれる。品格あるまちづくりというのは美学である。この考えは極めて論理的な自然の帰路でもある。
一九五〇年代の、つまり日本が本格的に資本主義的近代化の径につき進む前の日本の田舎の風景は実に美しかったと思う。決して便利ではなかったが、田舎の風景は美しかった。この事実はスペインの黄金艦隊が世界を制覇していた一六一七年のセバスチャン・ビスカイノの歴史的記述まで古くに遡る事もなく、一九二〇年代のドイツからの亡命者であったブルーノ・タウト氏の観察の記録にも示されている。一九五〇年代以前の日本の田舎の風景はその集落のたたずまい、そして自然の風景とのバランスに於いて世界でも有数なものを持っていた。品格のまちづくりなる鶴見等の考えは、要するに、リメンバー Pre 所得倍増政策のまち、なのである。
佐藤和則唐桑町長もかってそんな事を言っていた。日本の田舎の未来はいかに美しく枯れてゆくかしかないのではないかと。鶴見等の考えとほとんど同じものであった。しかし、それならば佐藤唐桑町長は気仙沼市との合併にブレーキをかけるのが理の当然であったろう。大きく考えれば気仙沼市だって縮小の一途への径を辿るしかない未来だ。合併して、つるんでのほどほどの静かな品格よりは一人独自な品格の径を行く美学の方が上等なのは誰の眼にも明らかだ。しかしながら当然、佐藤は熟練した町長として成長していたから、かくの如き原理的思考の性急な論理には組しない。政治は妥協という現実の連続だから。つづく
石山 修武
|
|
|
|
→ホーム
→インデックス
|
|
|
|
|
|

063 佐藤和則唐桑町長のこと
宮城県三陸リアス式海岸の小さな町、唐桑町。隣の気仙沼市と同様に、ここでは沢山の体験をした。一九八六年頃だったか、その頃から通い始めて、一九八八年の唐桑臨海劇場の開催。それは六年程続き、そして力尽きた。
佐藤和則は唐桑の地域おこしのシンボル的存在であった臨海劇場運動の中心だった。当時、佐藤は唐桑に帰って歯科医院を開業していた。都会の生活が長かったから、町では少し浮いていた記憶がある。もんもんとしていたのである。そんな時、東京からの流れ者の私と出会った。私は伊豆西海岸の小さな町松崎でいささかの仕事を終え、縁あって気仙沼市に呼ばれていた。マア言ってみれば気仙沼市の食客だった。気仙沼市は遠洋漁業の港町で、力もあり市の権力構造が仲々に複雑だった。それで市の有力者がしばらく隣の唐桑に行っていたらとすすめた。唐桑はシンプルだった。産業としての漁業の中心を気仙沼に握られ、その産業に漁船員を提供するしか無い様な土地柄だった。それだから若い人を中心に気仙沼市への負けじ魂があった。でも、どうする事も出来ないのだった。ただ、自然は息を呑む程に美しかった。海も山も森も。
全くの異邦人みたいにやってきた私と佐藤は良く退屈な時間を共に過ごした。佐藤は何処からか、突然やってきて、このカツオ節工場はこうしたら町営レストランになるぜ、とか、ここはこうしたらいいんだと、偉そうな口をたたく私の廻りを、野良犬みたいにグルグル廻り、吠えたり、時にかみついたりした。そうして少しばかり、銭金と関係の無い仲になっていった。
唐桑の数少ない大船主であった亀谷さんの使わなくなった工場を使って、劇場でも作ってみようかと言う事になった。妹尾河童や津野海太郎の考えも入っていた。佐藤がその実行委員長になって、その劇場作り運営の一切の責任者になった。毎夏の三日間だけ開かれる唐桑名物が一つ出来た。バブル景気は終末を迎えていたが、地方への波及は少し遅れたので、まだ何がしかの金が動いた。やがて当然の事ながら資金難。それで佐藤達は「町づくりカンパニー」なる会社を立ち上げた。今だったらNPOである。日本でも最初期の試みだった。唐桑の沿岸で獲れた魚を都会へと産地直送した。良い試みだったが早過ぎた。
臨海劇場は六年間続けられ、そして力尽きて中断された。しかし、若い人を中心に何かが残って、佐藤は町長になった。つづく
石山 修武
|
|
|
|
|
|
|
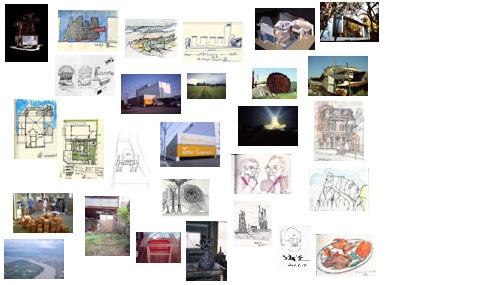
062 銀河鉄道計画8
南無妙法蓮華経を朗唱しながら、賢治が雪降りしきる東北花巻の町をうちわ太鼓をベンベンとたたき徘徊したらしきを知った時はいささか動揺した。新宿西口の地下街あたりでうさん臭い書物を売りつけている、クリシュナ新興宗教の連中や、現実にベンベン太鼓をうるさくたたいて布教活動している日蓮宗の一派の姿とダブってしまったからだ。宮沢賢治は良く知られるように東北岩手花巻の素封家、大きな質屋すなわち金貸しの息子だった。貧しい人々や百姓達の困苦を糧に商いをしていた家業に生活を支えられたドラ息子でもあった。賢治の純化された表現活動は東北の百姓達の地の塩をなめるような困窮があって支えられていた。イイ気なオッちゃんだったのだナァとも思うが、それだから賢治の表現活動が大きく傷つけられる事もない。が、いつの世もあまりにも神格化され、持ち上げられ、疑う事なく聖化され、それを犯すのを封印されたものは少なくない。現代はありとあらゆるイコンがクラッシュしている時代である。 9.11 ワールド・トレード・センターの崩壊に象徴されている如くに、最強である筈の資本主義社会のイコンでさえも、宗教的原理の相違によって崩れ去ってしまう。その崩壊の現場はTVによって世界中に同時に伝えられる。伝えられる側の内で何かが不安の発生と共に崩壊していく。伝えられる映像はほとんど世界共通でも、それを受け取める側は常に一人だ。一個の人間が老いも若きも一個の感覚、知覚を介して現実世界に対峙している。そして、個人の内部の崩壊が始まり、内的な廃墟が広がり始めている。
銀河鉄道計画と思いっ切り俗っぽい名をつけた計画をすすめている。それこそ同時多発的に。計画が実現されて現実に姿を現すモノもあるだろうし、計画だけに終わるモノもあるだろう。それは大きな問題ではない。イコンがクラッシュし続ける現実社会では現実と非現実のボーダーさえも崩壊しているのではないか。
宮沢賢治が日蓮宗のうちわ太鼓をベンベンたたき鳴らして雪降る花巻を歩き廻った現実も、南十字ステーションが登場する銀河鉄道の夜の非現実も何処に違いがあるだろうか。ボーダーは無い。その消え去ったボーダーを走らせるのが連鎖したスタイルを持つプロジェクト群になる。
この連続コラム自体の設計にもそんな趣向が意図されているのだが、まだまだ連なりが短か過ぎてその意図は伝わってはないだろう。
カバーコラムの一部はヴァーチャルな銀河鉄道の車窓から眺める現実の風景でもある。コンピューターの画像の枠も一種の窓である。皆さんはその窓を介して私を眺めている。窓の中にもう一つの窓が設定されていて、その窓からの風景は時間と共に流れ、移る。ただただ散乱した廃墟の風景に視えるだけか、雨の夜の鈍行列車の月並みな感傷の連続だったら当然大脱線状態、運転不能なのである。
コンピューターのフレームは明らかに新型式の窓だ。光や風を入れたりしないが、あらゆる書物と同様に知覚を働かせねば動かない列車の窓だ。私の窓をのぞき込むしばしの時は私の設計した列車の窓から走りながら外を眺めているのと同じ事なのです。鉄路を走る列車ではないから、レールの継ぎ目の音はひびかない。でも何か音にならない声らしきが聴こえてくるかもしれない。
石山 修武
|
|
|
|
|
|
|

061 アベル・エラソ
研究室には多くの外国人学生が在籍している。アベル・エラソは南米チリからの留学生だ。大学院に在籍しているが彼は三十才の気鋭の建築家でもある。実にセンスが良い。
世界中に忘れ得ぬ学生達がいる。ハンガリーの、屈強きわまりない学生はしばらく滞在していたドイツのバウハウス建築大学までヒッチハイクで何千KMも旅をして会いにきた。彼もすでに実作に近いプロジェクトを持ち、それにクリティークが欲しいとそれだけの為だった。リノ・バンチェラに似たしぶい男前で、バンチェラ同様鼻筋が少し曲がっていた。何かあったのであろう。プロジェクトを見ながら二時間程議論して、彼はワイマールからハンガリー迄、又、平然と戻っていった。金が無いから当然帰路もヒッチハイクだと言った。そんな事が一向苦にならぬ位に彼も建築が大好きなのだった。この男はいずれ世界の建築界に出てくるだろうと思った。時々、ヨーロッパの情報に触れる度に、私は彼の名を探すようになった。いつか機会があれば日本で仕事をしてみたい、その時はアンタのところで面倒見てくれるかと聞くので、いつでもイイヨと答えた。「でも、到底無理なんだ、生活が苦しくて、外国に出るのは夢の又、夢さ」とバンチェラは暗く笑った。時々、辛い事があったりの時には彼を思い出す。負けてたまるかと思い出す。
リオデジャネイロ大学の女学生Gもサンパウロまでバスを乗り継いでやってきて、私にそれは見事なプレゼンテーションをかましてくれた。自分より若いゼネレーションからショックを受けた初体験であった。彼女のプレゼンテーションは「まぶたが垂れ下がってしまう風土病になった人の為の眼鏡のデザイン」でそれをブラジルの貧困の問題と正面から向き合い、小さな眼鏡のデザインの背景を堂々と大部の社会背景、歴史から説明した。堂々たるモノであった。エルネスト・チェ・ゲバラがこんな風に南米の女学生に継承されているのを知った。設問の方法が見事だった。自分で問題を作り得ぬ日本の学生達とは、それこそ雲泥の差があった。
チリからのアベルにも彼等に一脈通じるものがある。何しろデザインが好きだ。三度の飯よりも好きだ。試しに彼に星の子愛児園の増築のデザインを担当させてみた。良い形を産み出した。不思議に洗練された形をひねり出すのであった。しかも、そこはかとない力が感じられる。すでに日本人の学生達には薄いエネルギーである。
最近、彼の処女作がチリに実現したと言うので写真その他を見せて貰った。モダニズムの大筋と第三世界特有のエネルギーがミックスしたものであった。渦巻き状の断面と平面を持つ、強いコンセプトが実に品格を持ったモダーンデザインとして洗練されていた。しかも、テント設営の原理を建築化したと言う。中々良いではないか。
新しい建築は彼等の様な地政学的ギャップを持たざるを得ぬところか生み出されるかもしれぬと思う事がある。建築、デザインの力を疑う事無なく、他の何よりも好きで、好きでたまらないという連中によって再生されるかもしれない。
本能的に洗練を知っているアベルには、君ね、チリ・バロックを今のうち勉強しておいた方がイイヨと無理難題を吹きかけている。彼だったらその難問中の難問を料理できるかなと思うからだ。我々は重源の大仏様を遂に継承できなかったからなあ。
石山 修武
|
|
|
|
|
|
|
 
060 ひろしまハウス2
ひろしまハウスが建設されているプノンペンの仏教大寺院ウナロムはポルポト政権時代、その本殿はポルポト軍の総司令部として使用されていた。首都プノンペン、及びカンボジア全土を制圧するに地の利があったからだろう。ワット・ウナロムはメコン河とトンレサップ河が合流する地点に近い。カンボジア王宮であるシルバーテンプルはすぐ隣だ。
ワット・ウナロムの本殿は壮大な境内の東に在る。トンレサップ河に面する。ひろしまハウスは境内の西端に位置する。
建設中のひろしまハウスの五階テラスに登り、東を見はらすと母なるメコン河がそれこそゆったりした水量で蛇行しているのが眺められる。テラスに腰をおろし、メコンからの風に吹かれているのは気持ちが良い。ウナロム本殿も間近に眺められる。
カンボジア王国を結果的には壊滅状態にしてしまったポルポトは極端な毛沢東主義者であった。都市という資本主義的産物を否定し、全土を農村化しようと試み、実践してしまった。都市の知識階級と覚しき人間の殆ど全てが殺戮された。眼鏡をかけているだけで投獄され殺されたという。当然教師の大半は殺された。謂わゆる教師達は近代化の大前提に乗った教育システムの歯車で、全ての国土を農村化する等という考えにはついて行けなかった。ポルポトは原理主義者であった。
テラスに腰をおろし、かってポルポトの居たウナロム本殿を眺める。ポルポトが本殿から眺めたようにメコン河を眺め渡す。ポルポトは殆んど無人状態になったプノンペン市の廃墟の向こうにメコンの河面の輝きを遠望しただろう。
どうして原理主義者達はかくも急ごうとするのか。近代が達成してしまったものを全否定しなくてはあり得ぬ原理の存在は想像し得る。それ故、ビン・ラディンはワールド・トレード・センターを破壊し、米国と戦争を始めた。ポルポトはアジアのパリと言われたプノンペン市を廃墟にして、住民を皆、メコンの大河が潤す農村へと移動させた。全て、自分が生きている間に原理のゆき着く先を見たいという早急な我執による誤りである。
しかし、原理そのものの形式に悪があるというのも誤りだ。原理的思考の何がしかには本格的な希望が垣間見える事も認めたい。時間が必要なのだ。五〇年単位、百年単位の時間への想像力が必須なのではなかろうか。しかしながら、あらゆる原理的な考えは必然として時間を急がせる性格があるとしたら、原理主義的傾向は時間そのものを意識するが故に、速力を希求するとしたら・・・と遠いひろしまハウスの風を思い出しながら考え込んでしまう。良質な原理主義的近代史を読んでみたい。
石山 修武
|
|
|
|
|
|
|
 
059 ひろしまハウス1
私が細々と積み上げている開放系技術・デザイン世界の近親者を挙げるならば、ウィリアム・モリス、B・フラー、コンラッド・ワックスマン、チャールズ・イームズ、J・プルーヴェ、川合健二、剣持怜、と多士済済だ。決して根無し草ではない。ただしウィリアム・モリスを除いて、皆、歴史、風土からスッパリ切れた、今で言えば超モダニスト達である。もう一つあり得たかも知れぬ道だったかも知れぬという意味ではヴァーチャル・モダニストと呼べなくもない。モダーン・デザインの主流は彼等とは別筋を、あるいはもう少し表層を流れた。唐突に言うがモダーン・デザインのベースは教育であった。モダーン・デザインの解りやすい出発点の一つであったバウハウスが教育的場所であった事にそれは端的に表れている。デザインを教えるには当然理論が無ければならない。と言うよりも解りやすい価値基準が無ければ教える事が出来ない。教える事が出来れば普及するのは速い。モダーン・デザインの基礎となった純粋幾何学はそれに適していた。近代の建築生産システムにも適うものだった。大量生産の方法は必然的に繰り返しが誤りなく持続する事を求める。その結果としてのモダーン・デザインであり、それを良しとする近代の教育システムがあった。近代の教育システムは基本的には大量生産システムに向けての標準化・統轄であった。カンボジアの「ひろしまハウス」の設計・建設はそれとは少しばかり異なる方法が試みられている。
かって、佐賀県の支援を受けて、三年間運営された早稲田バウハウス・スクールはドイツ国立バウハウス大学と協同のワークショップであった。数々の名講義があった。音楽家高橋悠治の佐賀の子供達への音楽教育が印象的な講義の一つだった。高橋悠治の言った事を私なりに要約すると、秩序だったリズムを共同で作り出す事は実に容易で、無秩序な状態を作り出すのは実ワ困難な事なのだという事である。高橋は竹筒等を使い、子供達にパレードの行進のように秩序だった、つまり全体を標準化する事に従うのは実に簡単な事を体験させた。次にそれに従わずにバラバラな状態を作る事が実に困難である事を示してみせた。子供達にも私にも学生達にも面白い体験だった。
ひろしまハウスは主体構造は近代のコンクリート構造で人工大地を何層か作ったが、その構造の上に作られる壁や、周囲の壁はワークショップ参加者によるレンガ積みによって建設されている。レンガ積みのデザインは当事者、つまり参加者に任される。キチンとした積み方が好きな人はそれなりに、キチンと積めない人もそれなりに、何か表現したい人はそれなりに出来るだけの事を。
使うレンガはカンボジア製の不ぞろいな日干しレンガ。完成状態に近づいた時に、この試みがどんな空間を産み出す事ができるのか私にも充分には把握できていない。個人の自由の表現がいかに困難な事でもあるかを示すものになる可能性だってある。
石山 修武
|
|
|
|
|
|
|
海軍省本部の塔
1806-1823
A.ザハーロフ |  | ペトロパヴロフスク聖堂
1712-1733
D.トレジーニ |  | |
058 アレクサンドロ・ソクーロフ2
ソクーロフの映画、特に「精神の声」から得た印象から、ソクーロフが近代の人間が深く対面せざるを得ない悲劇が主題の一つになっていると知った。「精神の声」の終りの独白から彼はサンクトペテルブルグ(レニングラード)を故郷とするのではないかと勝手に想像したが、それは誤りであった。西シベリア・イルクーツク市出身のようだ。一九五一年生れ。しかし生誕地がそのまま精神の故郷になるわけではない。三〇代のはじめに映画制作を始めた。レニングラード・スタジオ、レニングラード記録映画スタジオがソクーロフに影響したのは間違いない。
私のサンクトペテルブルグの都市、建築の記憶に鮮烈に残っているのは旧海軍省の建築である。ロシアン・モニュメンタリズムを良くは知らぬが、それとおそらく深い関係を持つのであろうスタイルを持った建築であった。例の、赤の広場や、クレムリンに見られるロシア伝統の玉ねぎドームに近い、もう少しアジア的なストゥーパの形にも似た重量感を持つ、軍事大国時代のソビエト連邦の力を彷彿とさせる、だからこそ、ソ連邦消失の今の時代とは歴史的違和感のある歴然たる異形の建築だった。それが在ることによって、一層の空虚を、決然とした力の消失自体を示している様な建築であった。何かが失くなった、居なくなったその事を痛感させる様なモノ。ロシア海軍省の建築のドームは黄金色に光っていた。ソクーロフもこの建築を日々眺めていたかも知れぬ。アジアに多くある黄金色に塗りたくられたストゥーパとは違う黄金色のドームは変なプロポーションを見せており、これがスラブ・バロックなのかとも思ったが、バロックと呼ぶには妙な脱力感があるのだった。脱力感というより、ソクーロフの映画に見られる画面のプロポーションの歪みのような、正しいヨーロッパの歴史主義の建築を水平方向ではなく、垂直方向に少し引き伸ばした様な異形振りが確かにある。パルテノン神殿のプロポーションはモダニズム建築の外形のバランスが考えられる際にも根強く影響を与え続けた。コルビュジェのモデュロールも、バウハウスのコンポジションにもそれはほとんど同じに影響を与えている。海軍省の建築のプロポーションはそれとは異なる、過剰な歪みがあるように思った。北国の空に暗鬱に光る黄金と共に、その歪みが都市の風景に不思議な脱力感を与えているのだった。厳密なプロポーションを欠いた退屈さ、しかもその退屈さは凡庸さとは明らかに異なっている。
石山 修武
→「精神の声」ソクーロフ、磯崎新
|
|
|
|
|
→ホーム
→インデックス
|
|
|
|
カバーコラムバックナンバー一覧←
|
→カバーコラム6
→カバーコラム8
|
|